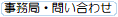#しつけと教育
作文が苦手な子を、親としてどう指導したらいいですか

小学生の娘は作文が苦手です。いつもごく短くしか書けません。「だって、書くことがないもん」と言います。夏休みに絵日記の宿題が出ましたが、先日娘の絵日記をのぞいたら、家族でご飯を食べている絵の下に「きょうもご飯を食べました」と1行書いてあったので、つい「あたり前じゃないの!」と叱ってしまいました。どうすれば、作文がうまく書けるようになるでしょうか。(小4女子の母親)

日記の宿題に頭を悩ませているというお話はよく聞きます。では、お話の中にあるような「ご飯を食べました。」の文ではいけないのでしょうか。
いえそんなことはありません。何を書こうかと迷ったときは、そんな話題になってもいいのです。ただ、それだけで終わらせないことです。まず、一緒に食べたことをテーマに選んだ理由を聞いてみましょう。
いつも忙しいお父さんやお母さんと揃って食べられたとか、大好きなおかずが並んでいたなど、書き込めなかった思いが引き出せるかもしれません。また、書くことに困って、ご飯の場面でも書こうとしたなら、どんなおかずが並び、だれとどんな話をしながら食べたのか、その時どのように感じたのかをゆっくり聞きながら、いつもの食事風景を言葉で描写していかせるのも一つの方法です。
お子さんと一緒に経験したことならば、その時のことを共に思い出しながら、言葉にしていくのです。そして、今話したことをそのまま文に書いてみるように促してみましょう。家族で話したこともそのまま、文に書き加えていきます。
鍵かっこを三つ以上入れようという条件を加えてもいいですね。すると、ある日の家族の姿が生き生きとした文章になって表されてきます。
もし、文に変えることに自信の持てない様子ならば、お子さんの話したことを文に起こしてあげるのも一つの手です。自分の話がこんな文になっていくのかと、感じさせることは次に書く時の役に立ちます。
ここで大切なことが、二点あります。
①.お子さんとの時間を、普段からゆったりと持てているか。一緒に見たものや、共にしたことについて、共感しあいながら、豊かな言葉で話しているか。
②.お子さん自身が、面白いとか楽しいと思えるような生き生きとした暮らしをしてい
るのか。これを書きたいという思いが湧き出るような毎日を送っているのか。
心も体も開放して思い切り遊べる暮らしや、人との繋がりが豊かな感性を育てていきます。
文を書く活動に端を発しましたが、単に書く技術を身につけさせるだけではなく、この機会に、お子さんが、書きたいことの多くある暮らしを作れているのかを見直してみてはいかがでしょうか。
村田 美保 (元小学校教諭:奈良実践国語作文研究会)

このお尋ねを読んで、思い出したことがあります。私も小学生の頃、作文が大の苦手でした。小4のお子さんの「だって、書くことがないもん」は、昔の小学生時代の私の声そのもののように思えました。実は同じ位の時に、親に出す手紙の文章が書けなくて、友人の文章をカンニングしたことがあります。
昔話になりますが、大2次世界大戦中に「学童疎開(集団疎開)」という措置が、日本の大都市で、学校単位で実施されたことがありました。私は小学4年生で親元を離れ、群馬県のお寺に何十人ものクラスメートと、集団で疎開生活をしていました。今さらですが、ネットを引いてみました。
「学童疎開―太平洋戦争の末期、不利な戦局下で予想された空襲の被害を避けるために、大都市の国民学校(小学校)初等科児童を個人または集団で農村地帯に移住させたことを言う。(中略)大都市児童の生命を守るため、1944年4年生から6年生の児童を半強制的に(農村部に)集団疎開させた」
私は当時、東京の両親と弟から離れて、群馬県のお寺に何十人ものクラスメートたちと寝起きしていました。授業などを受けた覚えはありませんでしたが、ある時、先生から親に手紙を書くように言われました。私は、ここでも書くことが思い浮かびませんでした。
ふと隣の子を見ると、長々と手紙を書いているではありませんか。ほんの一瞬でしたが「窓の外にはポプラの木が高く高く背伸びをしています」とあって、感心しました。その部分を私は親への手紙に借用しました。カンニングですね。戦争が終わって東京に帰った時に、親から「和子からの手紙は、ポプラの木が背伸びしているとしか書いてなかった」と言われました。苦肉の策でしたが、ダメだったのですね。
その私が、作文が苦でなくなったのは、父親の本棚に豊田正子さんの「綴方教室」を見つけてからでした。5年生か、6年生になっていたと思います。読み始めると、「ゆうべ」というタイトルで、ほうれん草をゆでる部分がありました(p17)。
「父ちゃんは浦和へ仕事にいって、まだかえらないので、私はかあちゃんがおいていった十銭で、前のかんぶつ屋のとなりの八百屋からほうれん草を買ってきて、おかまの火をもして、ゆをわかして、ほうれん草をあらっておかまの中に入れました。そのとき、ぱっと電気がついて、うちの中があかるくなりました(注1)。
私が、はしで、ほうれん草をひっくりかえし、ひっくりかえしして、赤いくきのところを手てつぶしてみたら、とてもやわらかなので、おけに水をくんできて、ほうれん草をおけの中に入れました。」(豊田正子「定本版 綴方教室」理論社1965)(注2)
少女が見たまま、したままを書いた文章でした。私は「なんだ!見たこと、したことをそのまま書けばいいのか。『今日もごはんを食べました』ではなくて、夕食のテーブルにいたのは誰と誰だったとか、おかずは味噌汁と魚の煮付で、魚がキライな私は残して、母親に叱られたとか、何でもできごとをそのまま書いていけばいいんだな」と。それ以後、私は作文がふつうに書けるようになりました。村田美保先生のような指導者がおられなかった時代の、ある小学生の体験です。
注1 昭和初期、定額料金払いの(貧しい)家には、電気会社が電気を夕方から朝方までしか送電せず、夕方になるとポッと家に(ワット数の低い)電灯がついた。街路灯も同様だった。
注2 追記:
何十年ぶりに豊田正子著「定本版 綴方教室」を読んで、感銘深いものがあった。発行者(小宮山量平)は、この本は1965年2月(第4版)までに70万部を売り上げ、時代の中で2つの大きな意味を持った作品であったと解説している。当時「国家に尽くすこと、天皇のために死ぬことが最高の名誉だった」時代の中で、身近な生活の輝きを捉えて教育のシン棒にしようとする「生活綴り方運動」が教師の中に起こっており、「綴方教室」は、いわばその一端を支えた作品であったという。また、日本の庶民の「貧乏」をすぐれた生態画として書き、そのエネルギーを一種の可能性としてとらえた作品であったとも解説している。
深谷和子(東京学芸大学:名)